自然免疫システムと遠隔転移の関係を究明し、人々が安心してがん治療に向き合える未来へ「がんの遠隔転移は予防できるのか?」
医学部附属病院 放射線部 助教
中島 良太
アジア・アフリカ地域研究研究科 准教授
佐藤 宏樹
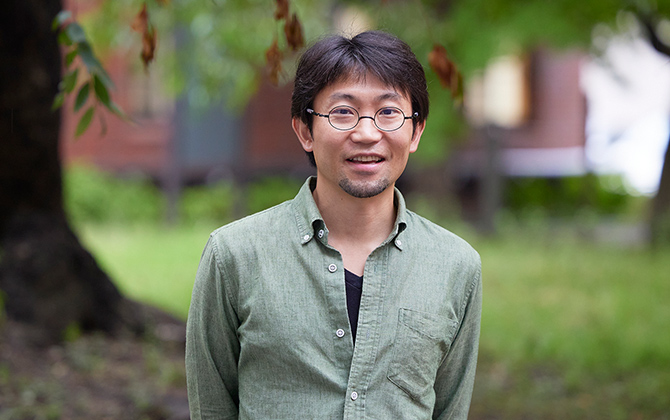
京都大学創立125周年記念事業の一つとして設立された学内ファンド*「くすのき・125」。このファンドは、既存の価値観にとらわれない自由な発想で、次の125年に向けて「調和した地球社会のビジョン」を自ら描き、その実現に向けて独創的な研究に挑戦する次世代の研究者を3年間支援するというものだ。
*「学内ファンド」とは、京都大学がめざす目標に向けて、京都大学が持つ資金を学内の教職員等に提供する制度のことです。
「環境保全と経済開発が調和する生態系デザイン」というテーマで2020年度に採択された佐藤宏樹先生は、マダガスカルのキツネザルから出発して植物、人、生態系デザインへと研究の視野を広げてきたという。豊かな生物相の保全と経済発展という2つの課題を抱えるマダガスカルで、どんな調和した未来を描くのか? 動画メッセージとインタビューで伺った。
先生の研究テーマについて教えていただけますか?
「私はこれまで、アフリカ大陸の東側に位置するマダガスカル島で、キツネザルが森をつくる働きについて研究してきました。
キツネザルたちはさまざまな植物の木の実を食べてフンを排泄するのですが、フンの中から種子が芽吹いて植物が育ちます。キツネザルが多種多様な種子を大量に、遠くまで運ぶことで、マダガスカルの森は豊かに保たれてきました。生態学ではこれを動物種子散布といい、生態系を理解する上で欠かせない現象なんです」

動物が森を育てるというのは興味深い現象ですね。その中でも、マダガスカルのキツネザルを選ばれた理由は?
「そこは大事なポイントですね。マダガスカルは中生代のジュラ紀にアフリカ大陸から、白亜紀後期にインド亜大陸から離れて孤島になりました。まだ恐竜が闊歩する時代で、大型の哺乳類がいなかった頃です。それからずっと大陸で進化した大型の動物が入ってくることがなかったので、猫よりも小さなキツネザルがこの島で一番大きな種子散布の担い手なんです。
大型動物による種子散布に関する研究は中南米のクモザルやバク、アフリカのゾウやチンパンジー、東南アジアのオランウータンなど世界中の森で行われてきましたが、動物相が貧弱なマダガスカルではこれまであまり研究されていませんでした。研究上のニッチということもありますが、小さなキツネザルがゾウと似たような役割を担っているかもしれないと思い、マダガスカル島を研究の舞台に選んだのです」
そもそもマダガスカルに行き着いたのにはどんなきっかけがあったのでしょうか。
「実は子供の頃にテレビ番組でキツネザルの特集を見たのがきっかけです。もともと動植物が好きだったんですが、キツネザルは原始的な霊長類として紹介され、いわゆる生きた化石というところにロマンを感じ、研究したいと思うようになりました。大学院に進学する際、キツネザルの研究が世界一進んでいた京都大学のアジア・アフリカ地域研究研究科を選びました。
初めてマダガスカルを訪れたのは2005年、修士1回生の時で、以前から現地で活動されていた京都大学理学研究科のチームに加えていただきました。まずは生態の基礎を知るためにキツネザルの行動を追跡しようとしたのですが、キツネザルは俊敏で全く追いかけることができませんでした。途方に暮れていた時に、目の前に落ちてきたキツネザルのフンに目がいったんです。せめて内容物を調べてみようとキャンプサイトに持って帰って洗ってみると、植物の種子が出てきました。それを植えてみると見事に発芽したんです。その瞬間にこれは研究テーマになると確信しました。それからはキツネザルの行動観察だけでなくフンの分析、植物の発芽実験など研究上の視界が一気に開けて、今日まで研究を続けてきました」

なんともドラマチックですね。その後、研究はどのように進展してこられたのでしょうか。
「種子散布について調査しているうちに、いろいろなことがわかってきました。キツネザルの腸を通過することで植物の発芽率が上がったり、遠くへ運ばれることで生存率が改善したりするという研究結果もその一つです。さらに、キツネザルがいないと発芽すらできない植物があることもわかりました。実が大きく堅い殻に覆われていて、同じく種子散布を行う鳥には殻を開けることができないのです。その証拠に、キツネザルのいなくなった森では、その植物もまた新たな芽吹きがないことがいくつかの研究で確認されています。
研究の転機となる発見は偶然訪れました。それは調査からの帰国前に、家族や同僚への手土産を買うために首都アンタナナリヴの土産物屋に立ち寄ったときでした。そこには蜂蜜や石鹸といった植物由来の製品が並んでいたのですが、その中にあったアロマオイルの原材料に、先ほどお話ししたキツネザルがいないと発芽できない植物の名前を見つけたんです。キツネザルと植物の相互関係の賜物が、現地の人々の文化や収入源になっているということが頭の中で繋がった瞬間でした。

そこから有用植物の利用にも関心が広がり、現地の人々への聞き取り調査へと発展しました。人々は植物の特性を熟知していて、昔からシロアリへの耐久性のある材木を選んで家を建てたり、解熱作用のある植物の葉を伝統医療に利用したりしてきたようです。近年ではそれが都市や先進国向けの製品になるということで、お金を得るための植物という価値観に変わってきている地域があることもわかってきました」
キツネザルから植物、そして人へと研究が広がってきたわけですね。それまでは野生動物を研究対象にされていたわけですが、現地の人々との関係はいかがですか?
「現地の人々は喜んでいろいろなことを教えてくれます。自分達の知識が国際学会レベルで通用することに痛快な達成感があって、みんな一生懸命に協力してくれますね。反対に私がキツネザルと植物の関係について教えると、『そんなこと知らなかった』と。そこでまたお互いの知識や価値観が更新されていくわけです。科学知と在来知の融合と言いますか、地域に入り込んで一緒に研究しているという感覚が面白いですね。生態学的なアプローチだけにとどまらず、地域研究との掛け合わせで全く違う成果を描いていけるのは、アジア・アフリカ地域研究研究科の特徴ではないでしょうか」

「くすのき・125」の応募時に説明された、先生の考える「125年後の調和した地球社会のビジョン」についてお聞かせいただけますか?
「125年というタイムスパンを自分では体験したことがないので、まずは今から125年前について調べてみることにしました。日本で言えば日清戦争の時代で、この頃から世界規模の戦争が繰り返されるようになります。燃料は石炭から石油に変わり、大量消費と経済発展を優先するあまり地球環境を徹底的にいじめてきた。今日までの125年間のうち、ほとんどはそんな時代でした。ごく最近になってようやく『環境と開発の調和』の必要性が訴えられはじめましたが、これを実現できない限り125年後はないだろうと考えています。低炭素社会、住民参加型保全、持続可能な開発……そうした新しいスキームを着実に実現させ、環境と開発の調和をめざすのが私のビジョンです」
先生の「くすのき・125」のテーマは「環境保全と経済開発が調和する生態系デザイン」ということですが、生態系デザインとはどういうことを指すのでしょうか?
「マダガスカルは生物多様性のホットスポットであると同時に、GDPは192カ国中186位という世界の最貧国の一つでもあります。環境を保全しながら経済発展をめざすという地球社会の課題を考えるのにぴったりのフィールドなんです。しかし近年、無計画な開発によって森林も人々も苦しめられているという現実があります。
とある調査中に、広大な森が、わずか数日の間に焼け野原になっているというショッキングな場面に出くわしました。キツネザル達が何百年もかけて育んできた森に、焼畑農業や木炭生産のために一部の人々が火を放ったのです。かと言って近隣の住民が焼畑を望んでいるわけではありません。貴重な有用植物が枯渇するだけでなく、森がなくなることで下流の水田に土砂が流れ込んで稲がダメになってしまう。マダガスカルの人達はお米が主食なので、これには困ってしまいます。また、キツネザルが安価な食肉用として違法に狩られているのも目にしました。森を育てて大きな価値を生み出しているキツネザルを、現地の人々は知らないまま絶滅へと追いつめているのです。これにはとても悔しい思いをしました。

そこで、森がもたらしてくれる恩恵について地域住民の人々と一緒に理解を深め、生態系とともに社会をデザインしていくということを考えました。生態系サービスと言って、豊かな生態系は人間にたくさんの恩恵を与えてくれます。有用植物はその代表例ですが、他の例を挙げると、キツネザルやカメレオンといった珍しい動物を観察するために欧米や日本から多くの観光客がエコツーリズムに訪れ、現地の収入源になっています。さらに住民は独自の知識や世界観などを森と関わることで培っていて、彼らの文化的なアイデンティティの確立や維持にも、森の存在が役立っています。
また、豊かな森林を保全することは国際的な要請でもあります。気候変動枠組条約に基づき、CO₂排出量の多い国や企業団体が少ない国や地域から排出枠(炭素クレジット)を買い取る仕組みが整備されてきました。これは途上国の森林を保全する活動に対して国際社会が経済的なインセンティブを提供するREDD+という枠組みとして注目されています。これらの仕組みを活用できれば、森林を保全すること自体を収入源にすることもできるかもしれません。保全と経済開発が調和する方法を探り、仕組みをデザインして実際に活用・運営していくことが目標です」
壮大な構想ですね。かなり長い道のりになるのではないでしょうか?
「時間をかけて基礎・応用・実践の3段階で取り組みたいと考えています。第一段階は森林や人々の営みについて深く知ることです。京都大学農学研究科の北島薫先生や、現地で京都大学と30年にわたって交流のあるアンタナナリヴ大学の研究者とチームを作って取り組もうとしているところですが、これだけでも数年はかかりそうです。第二段階は応用してシステムを作り出すことです。例えば河川の上流では野生動物や有用植物を保全しながらエコツーリズムで収入を得て、下流では水田で稲を育てる。自然の営みと人の営みの循環を理解して、住民の手で森林を管理しながら収益を得られるような生態系をデザインします。最後の第三段階では、それを長期的な視点で運営していきます。森の木々の成長速度や動物の個体数を増やすことを考えると、これにはさらに長い時間がかかるでしょう」
「くすのき・125」の採択期間の3年間ではどんなことに取り組まれる予定ですか?
「まずは人的な基盤づくりですね。2019年に前総長の山極壽一先生にマダガスカルまでお越しいただいて、京都大学とアンタナナリヴ大学で学術交流協定を締結したことが大きな一歩でした。アンタナナリヴ大学にも京都大学の出身の先生がいらっしゃることもあって、一つのチームとして生態系サービスや地域開発の課題に取り組んでこうという機運が高まっています。『くすのき・125』ではそのための拠点づくりや、両大学間での連絡体制の整備を進めていく予定です」
2大学での取り組みは今後どうなっていきそうでしょうか?
「125年先を見据えているわけですから、森だけではなく研究者の世代も更新していかなくてはなりません。30年続いてきた私達のチームはそれができているので、この先も長く続いていくのではないかと思っています。今も日本から学生を連れて行くとアンタナナリヴ大学のチームの人々や地域の人々がしっかりお世話をしてくれますし、京都大学でもマダガスカルから来る学生を受け入れていて、今年3月に学位を取って帰国したところです。両大学の学生たちには、このフィールドで一緒に学んだことを足がかりにして研究者として羽ばたいていってもらいたいと思っています」

アジア・アフリカ地域研究研究科 准教授
京都大学アジア・アフリカ地域研究研究科博士後期課程修了。2016年より同 助教。2020年4月より現職。専門は熱帯生態学・霊長類学。マダガスカル北西部の熱帯雨林でキツネザル類の生態を研究するほか、有用植物や生態系サービスに着目した地域研究にも研究テーマを広げている。