自然免疫システムと遠隔転移の関係を究明し、人々が安心してがん治療に向き合える未来へ「がんの遠隔転移は予防できるのか?」
医学部附属病院 放射線部 助教
中島 良太
化学研究所 柘植知彦 准教授
山口大学 農学部 肥塚崇男 助教
化学研究所 古田巧 准教授
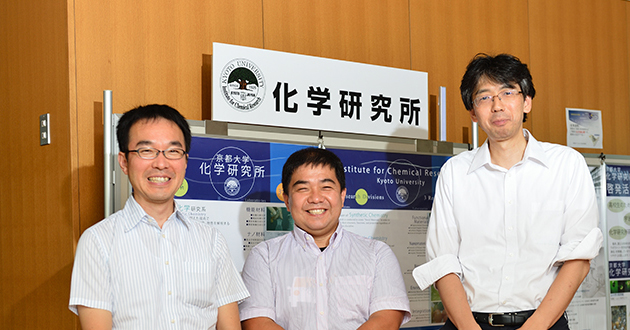
京都大学のキャンパスは大きく三つに分かれている。メインキャンパスの吉田キャンパスと「テクノサイエンスヒル」を目指す工学系の桂キャンパス、そして自然科学・エネルギー系の研究所が置かれる宇治キャンパスだ。この宇治キャンパスの研究者3人が、センター試験時の試験監督をきっかけに意気投合し、専門分野が違うにも関わらず、キャンパス内で咲く花について共同研究を開始。本業とは異なる分野のジャーナルに複数の論文を発表した。研究のきっかけや協力体制などについて話をきくと、京都大学だからこそ生まれた成果であることが見えてきた——。
化学研究所に所属する柘植知彦准教授と肥塚崇男助教(現山口大学助教)、古田巧准教授は、2013年1月20日のセンター試験で試験監督を担当した。同じ研究所内でお互い顔見知りではあったものの、それまで一緒に仕事したことはなかった3人が、試験監督の説明会で「試験後のお疲れさま会」を企画。お互い「植物好き」とは知っていたが、それほど深く話したことはないので、せっかくだから試験監督が終わった後に一杯やりましょうと、話がまとまったという。
柘植准教授は兵庫県生まれ。幼少時を米国で過ごし、日本の中・高を卒業後は早稲田大学理工学部に進学、応用生物科学で修士(工学)を修得した。その後、東京大学理学系研究科で植物の形態形成の研究で博士(理学)を修得。理化学研究所と米イェール大学、農業生物資源研究所を経て、京都大学化学研究所に着任した。自分のことを「根無し草」というが、京大に移って早15年。のびのびと自由に研究できる環境がありがたいと話す。
肥塚助教も兵庫の出身だ。代々続く味噌屋の息子で、小学校の文集で「世界一の味噌屋になる」と書いた少年は、後を継ぐつもりで山口大学農学部に進学。「発酵を学んでおけば役立つかな」というぼんやりとした学部選択で大学院にも進んだが、入った研究室で脂肪酸代謝に関する遺伝子を世界で初めて同定したことをきっかけに、研究者の道を選んだ。小さな発見だったと言うが「自分の目の前で誰も知らないことを知る喜びと満足感」に目覚めたという。専門は植物生化学で、今は主に「香り」を研究していることから、味噌屋を継がなかったものの将来は、味噌造りに適した大豆の品種改良や味噌の官能評価、分析などで、実家に貢献できればと考えている。2009年に京大に着任し、2013年秋からは山口大学で研究を続けている。
古田准教授は広島出身。小さな頃から植物好きで、広島大学の研究者が主宰する「山歩きしながら植物を教える会」に小学校時代から参加した。高校まで、老若男女問わず多くの人々と山歩きしながらたくさんの植物に接して育ち、岡山大学薬学部に進学した。植物好きだったことから、修士課程まで薬用植物を中心に研究。「生き物の機能を解明したい」と思いつつも、所属が薬用植物関連だったことから、化学が大切だと考えて合成化学分野に進んだ。
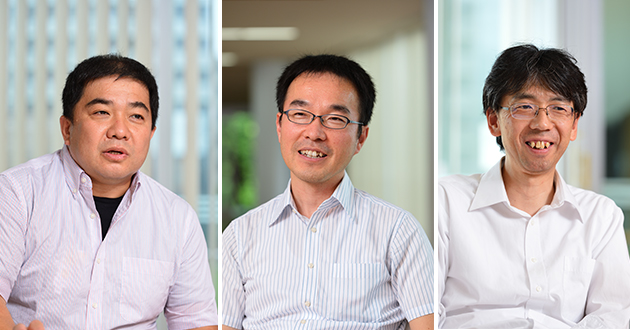
化学研究所というChemistryが中心の環境で生物をやっている研究者はそれほど多くないため、「植物好き」という接点で繋がった3人が仲良くなるまで時間はかからなかった。3人はセンター試験終了後、とある植物の名を店名に冠した居酒屋で、店名の植物や生薬の話などで盛り上がる。その中で話題に上ったひとつが、宇治キャンパスでセンター試験の季節に香るビワの花だった。
宇治キャンパスは面積21万平方メートル超と、甲子園球場約16個分の敷地面積を持つ。構内には建物も多いが緑も豊かで、季節ごとに様々な植物が花を咲かす。初春にはロウバイやジンチョウゲがよく香るが、12月の終わりから1月にかけてはヒイラギナンテン、ビワなどが花を付けるという。植物好き3人は杯を重ねるごとに、キャンパス内にひっそりと根を張る植物の「詳しさ」を競い始めた。そこから話が広がり、興味はビワの花の香りに集約した。3人とも、ビワの花がセンター試験の季節に咲くこと、特徴的な香りがあることは知っていた。宴会の席で3人は、「あのニオイはすごく重たい香りで、何の臭いなんだろう?」とひとしきり議論した。(主に地中海近辺で作られるアニス酒にいれる植物の)アニス系?どんな化合物が含まれてるんだ?といった様に盛り上がった。

一般的に研究者が集まった飲み会は、自由闊達な議論で盛り上がることが多い。だが、飲み会の席で出るアイデアは荒唐無稽なことも多く、夜が明けると「酒の席での話題」で終わってしまうことも少なくはない。しかし、この3人はそれだけで終わらなかった。肥塚がすぐにビワの花の香りを調べ始め、飲み会のあった週末にはビワの花の香りを分析し終えてラフなデータを柘植と古田に送ったのだ。肥塚は、「ビワの花のニオイがそれほど強いとは知らなかったんですが、言われると確かに強い香りだなと思って。何かしらあるかな、という感覚があったのと、せっかちなんでコレだと思ったらすぐにやらないと気が済まなくて」と話す。
柘植と古田は、翌週には出てきたクロマトグラフィーのデータを見て、「もうやっちゃったの」「早い」「すごいなあ」と感心した。そして3人は「この香りの物質には何かあるかもしれない」と感じ、ビワの花の香りをテーマに真面目に取り組むことで話が進んだ。幸いなことに、サンプル(試料)はキャンパス内にある。柘植は、「徒歩圏内にサンプルがあるのは大きい。夜の8時くらいになってからでも、必要なら取りに行けますから。ある年は、園丁さんが花を全部切っちゃったことがあったんです。切らないで下さいってお願いしたら、翌年からは大事にとっておいてくれて。ありがたかったですね」と、研究に着手した当時のことを回想する。
冬に咲く「ビワの花の香り」に注目した3人は、それぞれの専門分野でビワの香りを紐解き始めた。まずは花の季節に必要な試料を確保し、花が終わった後で様々な実験に取りかかった。
「香り」のメカニズムは複雑で、香りの「物質側」と、香りを「認知する受容側」とで、それぞれ機構が違う。3人が見ているのは、香る物質側だ。何かが香るには物質が「揮発」しないと受容側に「香り」として認知されない。そのため、揮発性物質を生成する「酵素」が働く。酵素は「遺伝子の発現」によって作られる。遺伝子が発現する時はDNA(デオキシリボ核酸)の遺伝情報を写し取るRNA(リボ核酸)がたくさん現れる。このRNAを見ることで遺伝子の配列が分かり、関与する酵素の目星がつく。
こう書くと、最初から謎解きの方向性が決まっていたように見えるが、実は色々な場面で紆余曲折があった。幸運だったのは、謎解きの重要な場面で、3人の得意とする研究分野が十分に発揮できたことだった。
柘植は植物の形態形成が専門分野で、形態形成のメカニズムを分子レベルで解明しようと、遺伝学や生化学などを組み合わせて研究している。柘植にとって分子生物学的なアプローチは「道具」であり、RNAの取り出しや遺伝子の同定などは得意なジャンルだ。宴の席で注目したビワの花は、すぐ近くで咲き乱れている。詳しく調べられる量のRNAをとるには最適の季節で、材料は簡単に手に入る。そこで、RNA抽出に取りかかった。柘植にとっては簡単なはずの作業だったが、実は最初はなかなかうまくいかなかったという。
「バラ科のビワが、この季節に花を咲かせるというのに興味があって。真冬のポリネーター(花粉媒介者)は何なんだろう?と思ったりしました。ある意味、季節商売ですから、花が咲いているときにRNAたくさんとっておこうと思ったんです。花が終われば無理ですから。ところが、最初はうまくいかなくて。自分の専門なのに悔しくて、いくつか工夫してまとまった量が取れたときには2人に『ほら、取れたぞ』って自慢する写真を送りました」
まとまった量のRNAを手にした3人のうち、次に動き始めたのは肥塚だ。専門は、植物の代謝や香りに関する生理活性物質の生合成や生体触媒。取れたRNAから生合成遺伝子を単離し、その酵素の活性を調べようとした。ある程度は、結果を予測して取り組み始めたものの、柘植と同じく最初はうまくいかなかった。
「ビワから単離した遺伝子を使って酵素を作り出し、機能を解析しようとしたんですが、酵素が失活(活性を失うこと)してしまって。原因の解明に少し時間がかかりましたが、なんとか酵素の精製に成功しました。原因解明には、自分の経験が役立ったのかな。なんとなくおかしいな?と思った生化学的な『勘』が当たったんだと思います。その酵素の機能解析を始めようとしたんですが、市販の基質がないので古田先生に合成をお願いしました」
酵素の働きを受ける物質を「基質」といい、一般的に酵素は働きかける基質が決まっている。そのため、酵素の機能を調べるには、その酵素に「適合した」基質が必要となる。ここで、合成化学が専門の古田の登場となった。
「こんなものが欲しい」と依頼された物質を作るのは創薬そのものであり、薬学の古田にとっては自分の十八番だ。「基質がないから作ってといわれて、4カ月くらいかけて作りました。化合物の合成そのものはそれほど難しくはなかったんですが、精製に時間がかかりました。酵素の性質を探る重要な化合物ですし、不純物があると研究全体に迷惑をかけるので、慎重に精製しました。こればかりに集中している訳ではないので、少し時間がかかってしまいましたが」と淡々と語る。
3人の見事な連携プレーについて肥塚は、「分野が近いといって、やれと言われてできるものではないんです。それぞれが持つスペシャリティが活かされたおかげ」と指摘する。また、「本業と離れたところで、のんびり長くやっていたのが良かったのかもしれない。この研究が、例えばどこかの研究費で採択されたプロジェクトで、締め切りがあったら、まとまらなかった」とも。
この、本業から離れた研究は、花のオフシーズン3回を挟んで実を結ぶ。2013年から2015年まで花と付き合い、本業の合間に解析を進めて必要な写真を撮影し、論文の形にまとめ上げていった。肥塚は2014年の秋に山口大学に移っており、3人が揃う機会は減っていたが、2015年度内には論文を投稿しようと目標を定めて地道に作業を続けた。3人が結実させた最初の論文は、植物学分野で伝統ある1925年発刊の『PLANTA』に掲載された。
『PLANTA』という伝統ある専門誌が認める成果となったのは、3人の専門分野が、異なるものの少しずつ微妙に重なっていることが大きかった。化学式は共通言語となり、それぞれが担当する実験は、実際にできなくとも説明されれば理解できる。かけ離れた異分野の研究者が集まっただけでは、学際融合的な研究を進めるのは難しい。しかし、柘植と肥塚、古田の3人は、植物好きという共通点に加えて、異分野で専門が違うけれども「どうやって答えを繋げていくか」の姿勢があったからこそ、出会ってから5年以上にわたって共同研究を続けられているのだろう。
研究の合間に集まって話しているときに一致したのは、「研究を楽しもう」という姿勢だった。3人は、「自分たちが面白いと思うことを、普段のメインのテーマとは別に、空き時間を使って効率的にやって、学生や周りから何やっているんだろう?って言われながらも、気付いたら論文になるってカッコいいよね」とよく話していたという。だからこそ、ビワの花の香りについては、がむしゃらにそればかりやっていたら、格好が悪いとも感じていた。3人とも、上司や学生との共著を気にせず、本業の片手間に余力でのびのびと謎解きを楽しんでいたのだ。
しかし、本業とは違うといっても科学的な研究であり、裏付けや検証は不可欠だ。そのために3人がそれぞれの分野で本領を発揮し、1人ではできなかったことを為し遂げた。柘植は、「分野ごとに、持っている情報やアプローチの常識は違います。研究は気分転換にもなりましたし、バックグラウンドの違いをそれぞれ面白いと感じて、そしてそれらは本業にも活かしていける知見にもなりました」と振り返る。
柘植が高品質なRNAをとって肥塚が酵素活性を確認し、酵素活性を見るために古田が不純物のない基質を合成するという、それぞれが担当した部分は、説明されればわかるものの、実際に手を動かせと言われても無理なものばかりだ。全く違う分野の3人が、植物好きを共通項に集まって、やり始めたら最後までやり遂げると一致団結したからこそ、まとまった成果に繋がった。しかも、それは、自分たちの分野のしきたりに縛られないで、柔軟性をもって取り組む必要があると、3人が理解していたことがポイントだった。
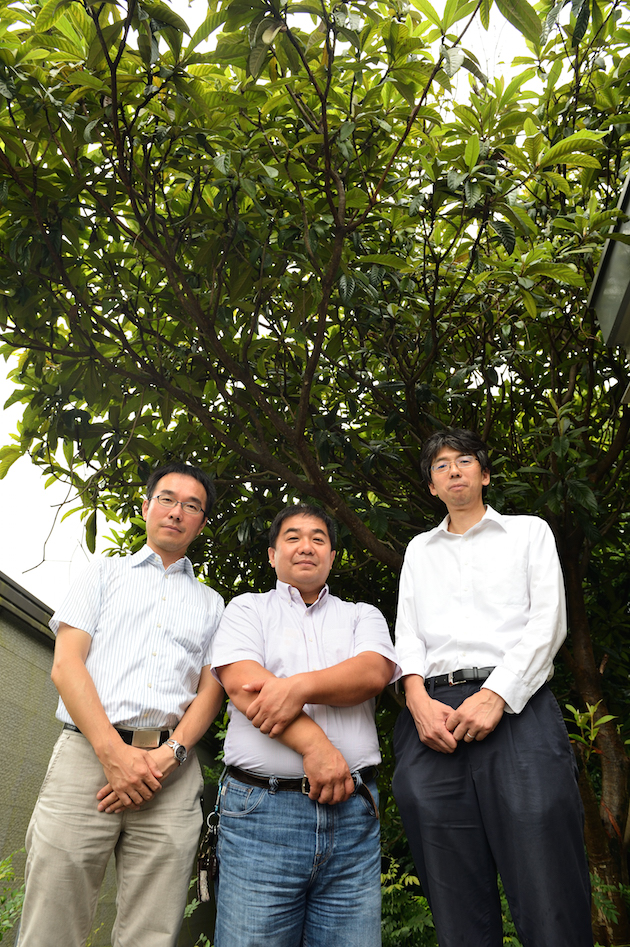
植物好きな古田にとって、自分の専門とは縁遠かった伝統ある専門誌に、3人連名の論文が掲載されたことはとても喜ばしいことだった。古田は、「僕は昔、こういうことをやりたかったんだな、と。2人と付き合うことで(昔の夢が)実現できているという実感があるので、楽しんでやっています」と話す。今の主な研究分野が薬学や合成化学となった古田にとって、合成化学ばかりだった業績の中に植物の論文が『PLANTA』に掲載されたのは、非常に感慨深いことなのだ。
発端は飲み会の席上の楽しい話題で、取りかかった当初は「それぞれ個人で論文をだせばいいか」くらいの軽い気持ちだったが、実際に研究を進めていくごとに幅が広くなり、そして成果につながった。成果は学会でも発表し、そして専門誌にも掲載された。最初の論文が『PLANTA』に載ったあと、3人はビワの花の香りをテーマに研究を続け、すでに合計3本の論文に加え、日本語コラムを発表。趣味から始まったものが、本当の研究に発展した。今は京都から離れた肥塚も、「2人にはいつもウェルカムでいてもらえて、とてもありがたい」と、何かあれば宇治キャンパスにやってきて議論を重ねている。まさに、宇治キャンパスを舞台に、異分野研究が花を付け、実を結び続けている。
柘植 知彦(つげ ともひこ)
化学研究所 准教授
→ 柘植 知彦 – 研究者 – researchmap
→ 柘植知彦/ホーム
肥塚 崇男(こえづか たかお)
山口大学大学院創成科学研究科 助教
→ 肥塚 崇男(山口大学 農学部)
→ 肥塚 崇男 – 研究者 – researchmap
古田 巧(ふるた たくみ)
化学研究所 准教授
→ 古田 巧(京都大学化学研究所研究者情報)
→ 古田 巧|京都大学 教育研究活動データベース
関連リンク