自然免疫システムと遠隔転移の関係を究明し、人々が安心してがん治療に向き合える未来へ「がんの遠隔転移は予防できるのか?」
医学部附属病院 放射線部 助教
中島 良太
工学研究科 教授
寺村 謙太郎
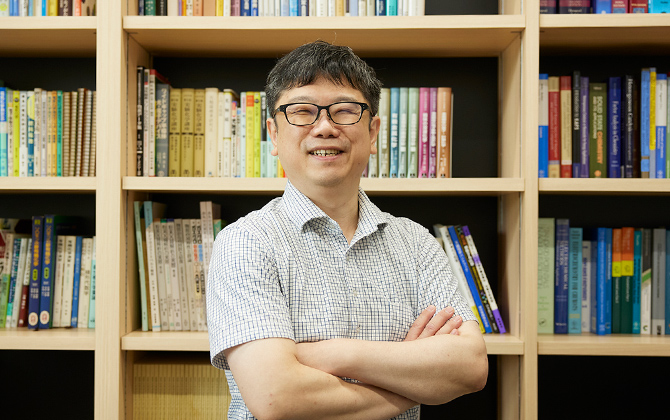
京都大学創立125周年記念事業の一つとして設立された学内ファンド*「くすのき・125」。このファンドは、既存の価値観にとらわれない自由な発想で、次の125年に向けて「調和した地球社会のビジョン」を自ら描き、その実現に向けて独創的な研究に挑戦する次世代の研究者を3年間支援するというものだ。
*「学内ファンド」とは、京都大学がめざす目標に向けて、京都大学が持つ資金を学内の教職員等に提供する制度のことです。
2021年度に採択された工学研究科の寺村謙太郎先生のテーマは「『たいよう』と『みず』の力によって実現するカーボンニュートラル」。光と水を使って、厄介者のCO₂を有用な物質に変える研究に取り組んでいるという。寺村先生がめざす究極の循環型社会とは?メッセージ動画とインタビューで伺った。
まずは寺村先生のご専門分野について教えてください。
「私の専門は触媒化学で、化学反応における触媒のはたらきを明らかにすることで、より優れた触媒を開発する研究を行っています。まず、触媒とは何かという基本的なところからお話ししましょう。
触媒とは、化学反応の前後でそれ自体は変化せず、化学反応の速度を速くしたり、必要な化合物だけを選択的につくったりすることを助ける物質のことを指します。使えば何かいいことがある、化学式には出てこない縁の下の力持ちといったところでしょうか。
触媒を使った化学反応で最も有名なのは、20世紀最大の発明とも言われるハーバー・ボッシュ法です。19世紀後半から20世紀初頭にドイツで発明されたこの反応をごく簡単に説明すると、熱した石炭に水蒸気をかけて水素(H₂)をつくり、その水素と空気中の窒素(N₂)を、鉄を触媒にして反応させることでアンモニア(NH₃)を合成するというものです。生成したアンモニアをさらに硫酸と反応させることで、小麦などの作物の肥料となる硫酸アンモニウムを大量生産できるようになりました。ハーバー・ボッシュ法のおかげで痩せた土地でも小麦を育てられるようになり、当時の急激な人口増加を支えるだけの食料生産が可能になったため、『空気と石炭からパンをつくる方法』とも評されました」
歴史を変えるような大発明にも触媒化学が使われていたのですね。寺村先生はどんな触媒を研究されているのでしょうか?
「ハーバー・ボッシュ法は窒素と水素を使いますが、私の場合は二酸化炭素(CO₂)を還元してさまざまな物質を合成する方法を研究しています。CO₂は構造式ではO=C=Oという二重結合で表されます。これは化学的に非常に安定、つまり他の物質との化学反応が生じにくい性質を持つことを意味しており、還元することは容易ではありません。ですから、CO₂を他の物質と化学反応させるには、外部からエネルギーを与えて反応を促進させる必要があります。そこで、私の研究室では光、電気、水素という3種類のエネルギー源のいずれかを利用してCO₂を変換するというテーマに取り組んでいるのですが、くすのき・125ではこのうち光からエネルギーを取り出して化学反応を促進する光触媒に注目しました。
もう少し具体的に説明しますと、CO₂と水を材料にして、光触媒を使って化学反応を起こして一酸化炭素(CO)をつくろうとしています。COというと一酸化炭素中毒を引き起こす危険なガスというイメージが強いかもしれませんが、『化学産業の米』と称されるほど重要な資源でもあります。COと水素ガスを混合した合成ガスが、メタノールやガソリンのほかあらゆる化学製品の原料になるからです。COは現在、メタンを主成分とする天然ガスを水蒸気と化学反応させることでつくられているのですが、ご存知のとおり我が国では天然ガスの供給を輸入に頼るしかなく、価格や供給量が世界情勢に大きく左右されてしまいます。CO₂からつくれるようになれば、化学産業に大きなメリットをもたらすでしょう」

実現すれば、温暖化と資源問題を一気に解決できてしまいそうですね。
「ところがそう簡単にはいきません。難しい課題がいくつかあるのです。CO₂と水と光から有用な物質をつくることは、つまり植物の光合成と同じことなのですが、まずこれを実現できる触媒を探し当てるのが非常に大変です。目的とする触媒を探し当てるには、触媒になりそうな物質をとにかくたくさん合成し、次々実験して性能を検証していくしかありません。しかもそのほとんどは失敗に終わります。例えるなら、ドリームジャンボ宝くじを一等賞が当たるまで買い続けるようなものです。
私たちはなんとか紫外線を照射することでCO₂を還元できる光触媒を見つけることができましたが、今のところ生成できるCOの濃度は1%程度です。これでも人間の致死量の5倍程度にはなりますが、工業用に使うにはもっと濃くする必要があるので、さらに効率のよい生成方法を追究しています。そのひとつの可能性が、くすのき・125でテーマに掲げた太陽の光、つまり地上に大量に降り注ぐ可視光線を利用することです」
非常に根気のいる研究であることが伝わってきました。先生はどうしてこの難しいテーマに取り組まれるようになったのでしょうか?
「私は京都大学の出身ですが、学位取得後に光触媒の第一人者である東京大学の堂免一成先生の研究室で特任助手をさせていただいていた時期がありました。堂免先生は水を分解して水素と酸素をつくる研究を長年続けられていて、そこで私も光触媒について学ばせていただきました。その後、京都大学に戻り、テニュアトラックの特定助手として自分自身の研究室を立ち上げることになりました。このときに新たに自分の研究テーマを決める必要があったのですが、同じアプローチで水の分解の研究を続けても堂免先生や先行する研究者にかなうわけがありませんでしたから、それならば誰もやっていないCO₂を対象にしようと決めたんです。
テーマを決めたは良いものの、学会などでは大抵『それは無理だろう』と言われました。普通に考えればCO₂そのものよりもCO₂を溶かしている水のほうが圧倒的に反応しやすいので、そう言われるもの当然です。ですが、学生時代からの恩師である田中庸裕先生だけは『触媒は性能が伴っていないと意味がない。やるなら半端な濃度ではなく、他の研究者を驚かせるぐらいの濃度のCOが出るような光触媒をつくってみなさい』と言って応援してくれたことを覚えています」

くすのき・125では、125年後に実現させたい調和した地球社会のビジョンについてお聞きしています。寺村先生のビジョンを教えていただけますか?
「太陽と水とCO₂から好きなものをつくり出せる循環型社会を実現したいと考えています。これまで、私たちは石油や石炭といった化石資源をはじめ、さまざまなものを使ってものをつくっては、最終的には燃やしてCO₂として大気中に排出してきました。その結果、資源問題や気候変動は年々深刻化しています。しかも地球の人口は増加する一方ですから、どこかで必ずエネルギーや食料といった資源の奪い合いが起こるでしょう。そこで私が提案したいのは、『自分で使ったものは自分で元に戻せ』という発想です。地球上に無尽蔵に存在する水や地球に降り注ぐ太陽光を利用して、一度排出されたCO₂をもう一度素材や燃料、あるいは究極的には食糧にリサイクルすればいいと考えました。
このように発想はシンプルなのですが、一朝一夕に達成できる話でもありません。究極の循環型社会が来るのが先か、人類が地球を捨てて火星に移住するのが先か……と授業では話していますけどね」
その循環型社会の実現に向けて現在取り組まれているのが、先ほどお聞かせいただいた水と光とCO₂からCOをつくる研究なのですね。どこまで進んでいるのでしょうか?
「触媒の性能を評価する基準として、活性・選択性・寿命という3つの要素があります。CO₂と水と光からCOをつくること自体には成功していて、次の段階として生成できるCOの濃度を上げたいと先ほどお話ししましたが、これは活性についての課題です。もうひとつ、触媒の選択性、つまりほしい物だけを得るという課題があります。
実験では、粉末状の光触媒を水に混ぜて撹拌しながら、そこにCO₂を供給し、紫外線ライトを当てます。このとき、生成したCOの半分量の酸素(O₂)が発生していれば、光触媒が狙いどおりに働いて無駄なくCO₂が還元されている証拠です。しかしCOやO₂に混じって水素(H₂)が発生していた場合は、その分だけCO₂ではなく水(H₂O)が還元されたことを意味するので、その触媒はCO₂を変換する効率が悪いということになります。
このように、私の研究室では、目的物質であるCOだけでなくO₂、H₂の生成量も精査して、一定水準以上の活性と選択性をもった触媒だけを独自にリストアップしています。リストに載せることができた触媒は、研究を始めた2011年から現在まででようやく19個になりますが、基準を満たさずリストに載せられなかった触媒がその100倍はあります。CO₂光還元の研究でこれだけ厳密な基準を設けて取り組んでいる例は少なく、私たちの自慢です」

くすのき・125で取り組まれる内容について教えてください。
「テーマに掲げた『みず』を使うことは成功しているので、つぎは『たいよう』です。先ほどお話ししたようにこれまでの実験では紫外線を使っていましたが、くすのき・125ではこれを可視光線で成功させたいと思っています。可視光線は紫外線と比べてエネルギーが低いのですが、太陽光として地球に届く量が紫外線よりも遥かに多いため、利用できるようになれば短時間でよりたくさんの反応を起こすことができるのです」
どうすれば可視光線から化学反応に必要なエネルギーを得ることができるのでしょうか?
「ポイントは触媒の色です。モノの色というのは、その物質が可視光線のうちどの波長の光を跳ね返すかによって決まっています。現在私たちが扱っている光触媒はほとんどすべて白い色をしています。白は可視光域の波長がすべて合わさった色、つまりその物質が可視光線をすべて跳ね返しているということですから、白い触媒では可視光線からエネルギーを取り出すことはできないのです。逆に言えば、色がついていてCO₂を還元できる光触媒を見つければ、可視光線からでもエネルギーや資源をつくることができます。
可視光線で化学反応を促進する触媒を可視光応答型光触媒といって、建物の外壁の汚れを防ぐ目的で使われる二酸化チタンなどで研究されている例もあります。ただし、同じ可視光応答型触媒といっても対応する化学反応はそれぞれ異なりますから、光からエネルギーを取り出せれば何でもいいわけではありません。候補となる物質がたくさんあるなかで、ひとつひとつ実験してCO₂を還元できる触媒を探していくしかありません。実はこれまでにも何度かチャレンジしていて、今回も非常に根気がいる挑戦になりそうですが、その泥臭さが面白いところでもあります」

ところで、水と光とCO₂からさまざまな物質をつくり出すというビジョンをお聞きしましたが、CO以外の物質をつくることも考えておられるのでしょうか?
「現在はCOしか生成できませんが、CO₂からギ酸(HCOOH)、ホルムアルデヒド(HCHO)、メタノール(CH₃OH)、メタン(CH₄)といったより生成の難しい物質をつくることにも挑戦したいと考えています。何が難しいかというと、水から取り出した電子をCO₂に素早く、たくさん渡さなければいけないのです。そのために工夫するポイントは複数あります。例えば、化学反応は触媒の表面で起きるため、触媒の表面積が大きい方が反応効率が良くなります。表面積を大きくするには、触媒の量は変えずに粒子を小さくするというのがひとつの方法です。また、電子が移動しやすいように、触媒粒子を綺麗に整列させるという方法もあります。もっと簡単なやり方としては、水を酸化するプロセス、CO₂を還元するプロセス、エネルギーを得るプロセスを別々に行う方法もあるのですが、すべての反応を一度でクリアできたほうが効率的ですよね」
メタンといえば天然ガスの原料にもなっていますね。その他の物質も耳馴染みがあるものですが、水とCO₂から合成できるかもしれないとは驚きました。化学者としての最終的な目標はどんなところにあるのでしょうか。
「化学はモノをつくり出す学問です。何をつくるか、どれだけつくれるか、いかに長持ちさせるかなど成果の評価軸がいくつもある分、実験で操作しなければならない要素も多いので、毎日が泥臭い実験の連続です。ですが、いつ成果が出るかもわからないかわりに、成果を出せたときは何物にも代えがたい感動を味わえます。私はその感動を知ってしまったので、すでにある1を10や100にする研究ではなく、0から1を生み出すような研究を生涯続けたいと思っています。
化学者としては、結合を切るだけではなく、繋げて新しいものをつくることにこそ醍醐味があると考えています。CO₂の二重結合を切ってCOにするのも大変なことですが、それだけで満足することなく、ゆくゆくは炭素どうしをつないで固体をつくるという領域にも挑戦したいです。CO₂を使ってカーボンナノチューブやグラフェンのような炭素材料ですとか、最終的には火力発電にも使える石炭がつくれるといいですね。目の前のテーマにも取り組みつつ、触媒化学だからこそ挑戦できる大きなテーマを探究していきたいです」
工学研究科 教授
2004年、京都大学大学院工学研究科博士後期課程 研究指導認定退学。博士(工学)。東京大学大学院工学系研究科特任助手、京都大学次世代開拓研究ユニット(テニュアトラック)特定助教、同大学工学研究科准教授などを経て、2022年より現職。専門は触媒化学で、光触媒の反応機構の解明や光触媒を用いた二酸化炭素の還元に取り組む。